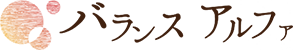「じゃりン子チエ」に学ぶ「おせっかい」
2020年12月30日
失敗や不幸を共有する理想の家族
「じゃりン子チエ」(はるき悦巳)は、1978~1997年の20年間にわたり週刊漫画アクションに連載された、大阪を舞台にした人情コメディー漫画です。
主人公の小学5年生の少女チエと、そのグウタラな父親テツを中心に、貧しいながら能天気に暮らす大阪下町の人々のほのぼのとしたドラマが20年にも渡る長期連載になったのは、そこに「日本の家族」の一つの理想形が描かれていたからではないかと思うのです。
連載スタート時のチエの家族は、毎日バクチに明け暮れて仕事もせず、何かというとすぐ暴力をふるう父親テツに愛想をつかした母親(ヨシ江)が家出し、チエがホルモン焼き屋を切り盛りして家計を支える崩壊家族です。
この状況を見かねたテツの小学校時代の恩師花井先生が介入し、母親が家に戻り家族3人のぎくしゃくした同居が始まるのが全67冊中の第1巻のお話です。
その後、この家族の周りにテツの両親(とくに腕っぷしの強い母親)や花井の家族、テツのやくざな友人たちやチエの小学校の同級生たちやその家族やどら猫たちまでがからみ、それぞれの個人や家族に発生する悩みや失敗や不幸を共有しあい、いつしか小さな笑いに変えて「明日は明日の太陽がぴっかぴかやねん。」とポジティブに生きていくエピソードが600話以上続いていくのです。
おせっかいが絆を深める「じゃりン子チエ」
面白いのは、誰かに何らかの事件が起こるたびに、登場人物のほとんどが、その事件に自らの意思で巻き込まれていき、結果として事件の出発点になった人物が、この関係者たちとの絆を強めることです。
事件そのものは、チエの同級生ヒラメの「どんくさい」というコンプレックスを解消することだったり、お好み焼き屋のオヤジの飼い猫の老衰だったり、テツのばくちのかたにお店がとられそうになることだったり、しょぼいことばかりです。
このしょぼいけれど当事者にとっては切実な事件に、周りの大人も子供も、なんとか力になろうと、おせっかいをしかけ、余計に事件がこんがらがる、というのは600話変わらぬ構造です。
ギスギスしやすい核家族
この「善意のおせっかい」こそが今日のポイントです。
家族とは、この善意のおせっかいの存在するところだということです。あるいは善意のおせっかいをする人々を「家族」と呼ぶ、と言い換えてもいいのではないでしょうか。
出発点の機能は、若い夫婦を中心とした核家族で行われますが、この核家族という形態は、父、母、子という各人の役割が固定され過ぎていることと、構成員の関係が(外に対して)閉鎖的であることで、往々にして息苦しくなり、家族関係が次第にギスギスしていく、というのが日本の現状です。
大切に感じる人はみんな家族
この固定的で閉鎖的という状態には風穴を開ける他者が必要となります。
外から他者を呼び込む仕組みが「善意のおせっかい」なのです。おせっかいの繰り返しの中で、いつしか内外の関係があいまいになり、血縁だからではなく、大切に感じる人だから、その人のために何かしてあげたい、という感情が起こる。それが「家族」である。その人の不在が寂しく感じられる存在、それが「家族」である。これが、私がひそかに日本人があこがれている家族像、ではないかと考える「拡大家族」というものです。
「善意のおせっかい」が必要なのは、家族という営みが本来一番弱い人を中心に成り立っているからです。幼子、老親、病に伏しているもの、心悩める人、それら一人では生きられない、生きにくい人を支えるおせっかい、それが家族を動かす動力ではないでしょうか。
1980年代から90年代へ、全世紀末の日本が経済的停滞と家族機能の不全で未来への希望を失っていた時代に、この「善意のおせっかい」の起こし方、畳み方を笑いながら共感し身につけられる、というい作品内容の人間的な面白味が「じゃりン子チエ」を長寿連載させた要因ではないか、と想像するしだいです。